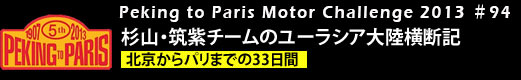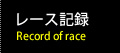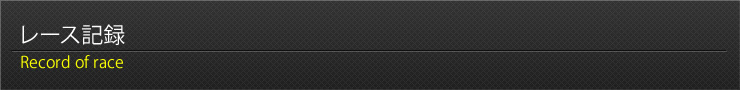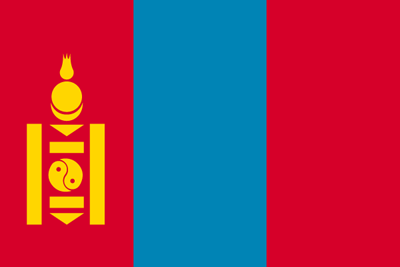Day4
2013.05.31
本日のルート
今日はウランバートルに入る日
ホテルチックイン後、すぐシャワー浴びたら、茶色の水が流れてくる。1回での風呂では落ちない
トランクの中までも砂だらけ
これで黄砂の原因が分かった。 なんとかしろよ、中国・モンゴリア
Sugiyama
第4日目、6月1日。5時に起床して日の出を見る。天気は快晴,寒くはなく涼しいという感じ。今日はゴビ砂漠のアルタンシレーからモンゴル高原のウランバートルまでの行程。これまでの2日間に比べて順調に進んだ。ラリーでは自分が走っている道が正しいか常に心配になり,昨日までは前後に車がなく,不安を抱えての走りだったが,今日は作戦を変えて,とにかく前の車についていくよう心掛けた。93番もベントレーで馬力があって早いので、これに何とか付いていけばその前の車をキャッチすることができる。道が正しければ引き返すロスも少ないので,大幅に時間を短縮できる。こうして明るいうちにチンギスカン・ホテルに到着した。
ゴビ砂漠のゴビは「窪地」を意味すると言われるが,実際に砂漠の中を走ると,行けども行けども砂漠があり回りに小高い山がある。その小高い山をすぎると,また砂漠があり回りに小高い山があるという風景。1907年の第1回北京パリのラリーでイタリアのボルゲーゼ公は,砂漠の中の電信柱を頼りに走ったと言われているが,まさに空と雲と砂漠の大地と電線しかない世界だったようだ。今でもこの光景はそんなに変わっていない。
モンゴル高原に入るとだんだん気温が下がり,山には残雪が見られるようになる。そしてこれまでの禿げ山から木の姿が見られるようになり,やがて高度1200メートルで盆地状のウランバートルに到着する。ちょうど夕方のラッシュアワー時で車の渋滞があったが,どの車も新しいというのが記憶に残った。経済が急速に発展しているのだろう。
今日は一日砂漠の砂を浴びたので,細かい砂が体中につき,また車の中やバッグ類の中にも入り込んでいる。それもあって明日の休養日にはバッグの中の物を整理し直す予定。
2日目、3日目と書き込む時間がなかった(夜になってホテルに着いた)ので,明日(6月2日)に,遡及して書く予定。
Chikushi

広大な砂漠
車内はもちろん、トランクの中まで
泥だらけ

テントレストラン
食事の種類は豊富
モンゴルでは羊毛産業が盛んなため
羊食は出なかった
キャンプ地のトイレ
撤収後は埋めるだけ。風通しの良いトイレだが、とても臭い。
外人どもは、何を食っているのか?肉食系は臭いと聞いた事がある
ちなみに、私(杉山)のはハーブの香りと言われた
キャンプ地
動物の糞が一杯であるので、テントを設営する際は、先ずは糞掃除からである
故障中
皆がいる所での故障、運が良い方である
全てが写真のような状態
砂漠のデコボコ道
ウランバートルに向かう前の記念撮影
スタートは常に最後の方である
まずはウランバートルに向けて、加藤チームスタート
この時は快調で、ウランバートルでは市内観光をする余裕
岩崎チーム (別名暴走老人)
凄い勢いで突走る
岩崎サンは歩く時も早足である
前方で、北見チームはスタート順番待ちこの悪路を競わせるのだ

トイレ探しにさまよう弁護士?
いや、スタート状況を見に行っていました。
スタートの列
彼は何を訊いているのでしょうか?
ちょっと用足し
年なもんで、又寒いし
Moive
Peking to Paris Motor Challenge 2013 #94 Sugiyama&Chikushi
杉山・筑紫チームのユーラシア大陸横断記「4日目」です。
次の動画は「9日目」です。